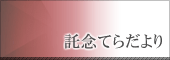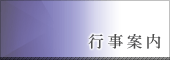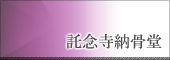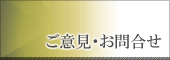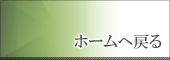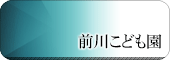254号 感話:いのちの重さ-シビ王と鳩と鷹の物語- [ 令和8年2月4日 ]
今季最大の寒波
 温暖化は冬の景色を変えました。この年齢になると屋根に上がって雪おろしをしたくありません。最後に雪おろしをしたのはいつでしょう。去年は2月に大雪に見舞われましたが、雪おろしには至りませんでした。どうかひどくならないでと少雪を願っておりましたが、寒波に見舞われています。その只中にいるといつ止むのだろうと天気予報を何度も確認し、天気予報が外れて欲しいとまで思います。朝の雪かきは骨の折れる作業ですが、出勤する職員に労いの声をかけてもらうと元気がでます。一緒に作業してくださる方がおられることで頑張ろうの気持ちが自然に湧いてきます。町内の方々からはこども園保護者の送迎がしやすくなるようにとさまざまに工夫をしていただいています。支えられていると嬉しくなります。
温暖化は冬の景色を変えました。この年齢になると屋根に上がって雪おろしをしたくありません。最後に雪おろしをしたのはいつでしょう。去年は2月に大雪に見舞われましたが、雪おろしには至りませんでした。どうかひどくならないでと少雪を願っておりましたが、寒波に見舞われています。その只中にいるといつ止むのだろうと天気予報を何度も確認し、天気予報が外れて欲しいとまで思います。朝の雪かきは骨の折れる作業ですが、出勤する職員に労いの声をかけてもらうと元気がでます。一緒に作業してくださる方がおられることで頑張ろうの気持ちが自然に湧いてきます。町内の方々からはこども園保護者の送迎がしやすくなるようにとさまざまに工夫をしていただいています。支えられていると嬉しくなります。
年末年始の御礼
 12月30日に本堂大掃除、仏具磨きがありました。お内陣からすべての仏具を取り出してほこりを払い、垂れたろうそくを落とし、真鍮の仏具は専用の薬品を入れたお湯につけて洗います。とりだしたものは復元しなければなりませんが、先輩方から引き継いだやり方を踏襲し年々の繰り返しで要領よく仕事が進みます。最後にお正月用の荘厳をして記念撮影です。清々しいお顔の皆様にこころより感謝申し上げます。
12月30日に本堂大掃除、仏具磨きがありました。お内陣からすべての仏具を取り出してほこりを払い、垂れたろうそくを落とし、真鍮の仏具は専用の薬品を入れたお湯につけて洗います。とりだしたものは復元しなければなりませんが、先輩方から引き継いだやり方を踏襲し年々の繰り返しで要領よく仕事が進みます。最後にお正月用の荘厳をして記念撮影です。清々しいお顔の皆様にこころより感謝申し上げます。
 31日の大晦日から元旦にかけて除夜の鐘撞きには大勢の参拝がありました。これを支えてくださる恵以真会の皆さんは明るいうちにテントを張り、かがり火の薪を確認するなど準備をしてくださいました。除夜の鐘撞きを終えて、ここでも清々しい笑顔に支えられていると、嬉しくなりました。
31日の大晦日から元旦にかけて除夜の鐘撞きには大勢の参拝がありました。これを支えてくださる恵以真会の皆さんは明るいうちにテントを張り、かがり火の薪を確認するなど準備をしてくださいました。除夜の鐘撞きを終えて、ここでも清々しい笑顔に支えられていると、嬉しくなりました。
サイノカミ-無病息災・五穀豊穣・平和への願い-
 祝日「成人の日」が固定ではなくなってからサイノカミも地域ごとに開催日がマチマチになりました。前島町は1月12日、午前中の天気に恵まれて小学生も手伝って立派にできあがりました。豊富なわらによって、燃えている時間も長く、見ごたえを感じました。帰路振り返って、雪原に映える姿を収めました。
祝日「成人の日」が固定ではなくなってからサイノカミも地域ごとに開催日がマチマチになりました。前島町は1月12日、午前中の天気に恵まれて小学生も手伝って立派にできあがりました。豊富なわらによって、燃えている時間も長く、見ごたえを感じました。帰路振り返って、雪原に映える姿を収めました。
安倍元首相銃撃事件 無期懲役
重い事件で重い判決だと思いました。死刑にならずに「無期懲役」であったことが、事件の背景になっている旧統一教会信者2世の不遇な生い立ちへの情状酌量であったと解釈することも可能かもしれませんが、無期懲役は社会復帰する道を閉ざす判決です。前号に保護司の仕事を紹介しました。社会復帰を支援する活動です。山上徹也被告は社会復帰を支援されるべき人間であると思います。銃撃して死に至らしめた犯行はどんな理由があっても許されることではないけれど、事件後に明らかになった旧統一教会と政治家の関わりの実態は永年放置されてきました。この事件がなければ、山上被告と同様の苦しみをかかえていた人がさらに困窮に追い込まれていたことも十分に推測されることです。この事件が起きる前にもっと山上さんを支援する手立てがなかったのか。この犯罪が重罪であることを十分に認めつつ、更生する道筋を選択肢のひとつに加えることができないのだろうか。上級審に控訴してその道が拓かれることを願いたい。
感話 いのちの重さ-シビ王と鳩と鷹の物語-
前川こども園の仏参行事:子ども報恩講で仏典物語を子どもたちに紹介しました。報恩講は親鸞さまのご命日です。ご命日とは仏さまになられた誕生日でもあります。文字通り、いのちを考える日でもあります。この時期になると、5歳児の成長した姿に1回1回の行事を大事にしたい気持ちにさせられます。
黒板に天秤ばかりの絵を描いて、「これは何だか知っている?」と尋ねました。「てんびんばかり」と声があがりました。「何をするものですか」と続けると「重さをはかる」と答えが返ってきました。天秤ばかりの原理を説明して、重さが同じ時に釣り合うことを子どもたちと共有しました。そして物語を始めました;
一羽の鳩がおびえた様子で王さまのふところに飛び込んできました。
鳩:「王さま、助けてください。鷹が追いかけてきます。私を食べようとしています。」
鷹:「王さまが今かくまった鳩を返してください」
シビ王:「鳩のいのちを護るためにお前に渡すわけにはいきません」
鷹「私はお腹がすいています。鳩を食べないと死んでしまいます。鳩を渡してください。王さまは私と鳩とどちらのいのちが大事だと思っているのですか。」
王さまは、天秤ばかりの一方に鳩を乗せ、家来から包丁を受け取ると、自分の太ももに包丁を当てて、ザバッと切り落としました。その肉を天秤ばかりのもう一方に載せました。ところが天秤ばかりは鳩の方に下がったままでびくともしません。王さまはそれならばと、もう片方の太ももに包丁を当てて、またバサッと切り落として天秤ばかりに載せました。それでも動きません。そこでようやく王さまはいのちの重さに気がつきました。自分の身体ごと天秤に載り移ると、それまで動かなかった天秤がちょうど釣り合って真ん中で止まったではありませんか。
シビ王:「鷹よ、私の身体を全部、お前に渡そう、そのかわりに鳩のいのちを助けて欲しい」
その言葉を聞いた鷹は、たちまち帝釈天に姿を変えて、「王さま、あなたは本当に慈悲深い人です。必ずや仏になって人々を救ってくださいます」と言い残して立ち去っていきました。 合掌